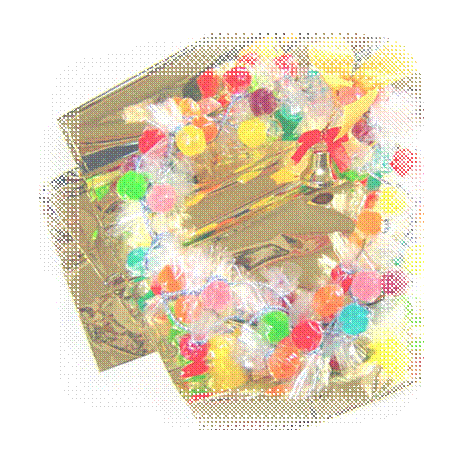
オレ、丹羽謙太は、聖なる気持ちをありったけ込めた握りこぶしを、胸にあてた。
世界のアベックごめんなさい。リアルが充実している皆さまごめんなさい。
そして、敬愛なるサンタさまへ。
もう爆発しろなんて言いません。絶対言わねぇので、いい子にしているので、
お願いだから。
お願いだから助けてくださああぁぁぁぁぁぁぁぁいッッ――
アメ売りの同級生と、赤鼻のおっさん……と、嫌々オレ
「おい丹羽、死にそうな顔してんぞ! 大丈夫か!?」
天(と書いてサンタと読む)へと放ちかけたオレの意識は、頬をぺしぺしと叩かれたことで身体に戻ってきた。
自分の白い吐息が電飾で明るい夜空に、溶けていく。
闇色の雲がラッピング用紙のように薄く、ひらりと空を覆っていた。
今日という寒い日に、駅近くの商店街はいつもよりも賑やかで、
人が働く空気があたたかく充満している。
こうして世の中が動いていくのだ、なんて神聖なのだろう。
政治家はこの空気に触れるべきなんだ。
この空気に触れないで、何が「国民のための政策」だ。
人の世の中は、たくさんの人々がこのように懸命に働いて、回しているのだ。
議会が回しているんじゃないのだ。ああ、なんていい空気なのだろう。
「今日は非常に聖なる夜だ」
さあ、もうすぐ時間だ――とバス停に向いたオレの足を、止められた。
「ちょおおぉぉっ、待てって! 待てって!! な、これやるからっ」
力づくで振り向かされて、両手いっぱいに握らされたのは、色とりどりの大きい飴だ。
近所のおばちゃんよろしく飴をこぶしにねじ込んできた奴の顔を、改めて見据えた。
「樅山――くん」
「“くん”いらねーっ、水くさいなぁ丹羽!!」
お前がなれなれしいんだバ――おっとサンタさんごめんなさい。
ウマシカなんて言ってない。言ってないです。
ちなみにオレの「丹羽謙太」っていう名前はかつて、
中2病のクラスメイトに「ニワってニワトリじゃーん!! チキン!! 謙太ッキーチキン!!」とからかわれたことがある。
あれはイジメだったのか?
まあ、実際チキンなのだ。
街中で、禁止されているはずのバイトをやっているっぽいサンタ衣装のクラスメイトを見かけて、声をかけられるほど、オレは勇者じゃない。
だから冒頭で逃げたかったんだ。本当に逃げたかったんだ。
それにそもそもオレ、こいつとあまりしゃべったことがない。
こいつ――樅山は端的に言えば、元気のいいデキスギくんのようなヤツだ。
つまり、顔よし、頭よし、運動神経よし、女子ウケよしで、
それなのに割と男子にも人気がある。
おいおいどれか分けてくれよと言いたくなるようなヤツだ。
オレとの接点なんて、体育祭とか文化祭とかの行事のときくらいだ。
そいつが、高校で禁止されているバイトを?
オレの心のもやもやを知らない樅山は、ふっとさわやかに笑みながら手を出した。
「はい100円ちょうだい」
「は?」
「アメちゃん代。いっこ10円だから」
お前ふざけるなよ押し売りじゃねーか
と思いながら口には出せないのがオレだ。
しぶしぶ100円を財布から出しちゃっているのがオレだ。
まあ、100円くらいだしな……。
100円を、樅山の手のひらに確かに置く。
「じゃ、また明日」
「だから待てってぇぇぇ!! アメあげただろ!!」
胴体にがしっとしがみつかれて、息が一瞬詰まった。
なんでこいつ、こんなにオレに絡んでくるんだよ。
「バイトの件なら黙っておくから離せって……」
面倒だからもともと言う気はなかったが、樅山がオレにしつこい理由といったら思いつくのはやはり、口止めしたいからだろう。
樅山はゆっくりオレから離れたが、逃げないようにするためか、オレの学ランのすそを引っ張った。
「言わないでおいてくれると助かる、けどそれだけじゃなくて」
樅山は手にぶら下げた木網みのかごに目を移した。
まだ結構な数の飴が入っている。
「これ、全部売り切らないと、家に帰れないんだよ」
「お前はマッチ売りの少女か何かか」
思わず口から出たツッコミに、樅山はぶはっと笑った。
ナイスツッコミ、とか笑いながら肩をバシバシ叩いてくる。
「オレな、修行中の身なんだ」
樅山はにこにこしている。女子はこういう笑顔にやられるんだろうが、今のオレにはなんだか嫌な予感しかしない。
「それで丹羽、今日一日だけでいいからオレのトナカイになってくれないか」
なん……だと。
「断る」
「逃がすか」
踵を返しかけたオレを見て、樅山はつかんでいた服のすそをぎゅっと後ろに引っ張った。
「首しまる首しまる!! やめろって」
「じゃあ承諾しろよな」
何なんだその「じゃあ」ってのは。
樅山は「そんな嫌そうな顔すんなってー」と笑みながら眉尻を下げた。
そんなこと言われてもだな。
「トナカイって、なんだよ。売り子手伝えってこと?」
迷惑だっていう気持ちを全面に押し出しながら、眉を寄せつつ聞いてみる。
トナカイの着ぐるみ着るとかイヤだぞオレは。
「んー、ちょっと違うかなあ。オレを、連れて行ってほしいわけだよ、夢も希望も持ってませんって顔した人のところに」
一瞬何を言われているのかわからなかったが、会話を成立させるためにとりあえずヤツの言い分を受け止めた。
「……そんな人はお金もないだろ。飴を売りたいなら別のターゲットにしろよ」
「金はとらないけど、報酬はもらうんだ」
至極当然、といったふうにオレに真剣な目を向けてくる樅山。
ああダメだ。もうダメだ。
オレはなんだか無性にいらいらした。
「オレからは金とったじゃん、わけわかんねぇ」
苛立ちをオブラートに包まず言うと、樅山は「金はとったけど、」と口を開いた。
「丹羽の不幸は、報酬にするには足りなかったんだ。だからいっこ10円で手を打った」
こいつの言っていることはやはりわけがわからない。
それなのに、なんだか。
なんだか、「彼女がいないとか友達がいないとかちっぽけな不幸なんて、くだらない、価値のない悩みだ」と言われた気がした。被害妄想、か?
フリーズしかかったオレの視界の端では、クリスマスのイルミネーションがちかちかと色を移していく。
「この駅にいる人でいいんだ。オレを連れて行ってくれ。
オレは――トナカイがいないと、仕事ができない」
にこりと、教室で振りまくのと同じ笑顔が、オレの目の前にあった。
こいつの笑顔って、なんか怖い。
本心で笑ってるんじゃないからだと気がついたのは、今だ。
こいつの笑顔は、商売道具の笑顔でしか、ない。
「早くしないと、聖夜が終わる。手伝って、くれるよね」
――価値のないあんたにアメあげたんだから
心の声が聞こえた気がして、オレはヤツの視線から逃げるようにうつむいた。
「……ああ、わかった」
小心者のオレが精一杯に呟くと、見ていないけど、樅山がにやりと笑った気がした。
オレのなかでデキスギくんが黒い悪魔と化していた。
そして、サンタが嫌いになっていた。
*** *** *** ***
手伝うと承諾してしまった以上、さっさと飴を客に売りつけて、帰ろう。
樅山と極力目を合わせないようにしながら、オレは行きかう人の波に目をこらした。
最初のターゲットは、このファミリーやらカップルやらで賑わう光の街中を、
独り道行くOLだったが、樅山が却下した。
あのOL、ずいぶん希望のなさそうな目をしていたんだが……大丈夫か?
お独り様で寂しそうな顔をしているヤツなんかはごろごろしてて、
こういうヤツは、樅山が却下を出すということがわかった。
不幸そうなヤツを見つけて飴を売るって、とんでもない商売やってるな、こいつも。
結局2時間駅周辺をうろうろして、ようやく樅山の許可が出た不幸人は、
客の来ない寒空の下で路上ライブ活動する赤鼻のおっさんだった。
寒さで赤くなったのか、酔って赤くなったのか。
おっさんは狂ったようにギターをかき鳴らし、叫び声としか言いようのない歌声を、唾とともに飛ばしている。
すりきれて砂だらけのスーツを着て、かけてるメガネなんかは右のレンズがはまってなくて、そこから覗く目はぎらぎらと怒り、悔しさに燃えている、ように見える。
ザビエルハゲで、ギターの弦のうち一本が、あらぬ方向へ向かって飛んでいる。
傍らにはネクタイやら靴下やらが散乱していて、つまりおっさんはこの寒中にはだしだった。
客が来ないのは、おっさんが暗がりで演奏しているからだけではない。
近寄れない。近寄りたくない。
近寄ったら最後、自分もこの不幸オーラに中てられて、感染してしまいそうな気さえする。
だって遠目で見ただけでこの気分なんだ。
他人を見て真剣に結界を張りたい気分になったのはこれが初めてだ。
ああ、樅山、オレの不幸なんてちっぽけでくだらなかったよ。理解したよ。
オレが悪かった。認める。
だからさ、悪いこと言わないから、この人だけはやめておこうぜ。
「トナカイくん、じゃあ行こうか」
「トナカイ」という言葉が、もう「パシリ」とか「下僕」あたりにしか聞こえない。
なんてオレが思ってると、樅山がとん、と軽く肩を叩いた。
「トナカイってさ、すっごい高い身分なんだよ」
今度は何だ……。
ひゅう、と冷風がオレたちの間を通り抜ける。もっと下に着込んでくればよかった。
樅山はおっさんに目をやりながら、自嘲気味に笑んだ。
「本当は、ベテランがやるんだよ、トナカイって。でもオレ修行中の身だから自分で見つけないといけなくって」
「その、修行中の身っていったい……」
ギャァァァァァァァァンッという豪音にオレの声がかき消され、耳にわんわんと響いて一瞬聴覚が使い物にならなかった。
おっさんのほうへ目を向けると、足取りもおぼつかないままギターを抱えて、ばかやろう!! と天に叫んでいるところだった。
さっきの爆音は、おっさんがギターをむちゃくちゃにかき鳴らした音だろう。
一度静かになるも、今度は何やら口ずさみ始めた。
耳をすませばそれはおなじみのクリスマスソングで――
「真っ赤ァなおっはなァのぉぉぉーおっさんはァァァァァいっつもみんなのォォォ笑ァいモン〜、あっひゃひゃははっはー!!」
もういい、もういいよおっさん。悲しくなるから……。
「おじさん、おじさん」
オレが目頭を押さえていると、いつの間にか樅山がおっさんに近づいて行っていた。
一人で行かせるのがなんだか怖くて、あわてて後を追う。
「何だね少年」
おっさんは案外しっかりした口調で樅山に応じた。普通にしていれば普通の人なのになぁ……。
「これ、オレからのクリスマスプレゼント。あげるよ」
戸惑うおっさんの手に、飴を両手から溢れんほどに握らせた。
背中を向けられてるのに、樅山が営業スマイルかましながらやってるってわかる自分が怖い。
「こんなもん、いらんわ!!」
おじさんは握らされた飴を樅山に投げつけた。
ばらばらとアスファルトに散らばる飴。
いくつかは樅山に当たったが、至近距離で投げられたから痛かっただろうに、樅山は痛いとも何も言わず、おっさんに向き合っていた。
「こんないい夜に、独りってさみしくない、おじさん」
樅山はゆったりとした動作で飴を拾い上げていく。
その拾った数個を、おっさんの手に押し付けた。
「オレ、わかるよ。だからせめてもの気持ち。
甘いもの食べるとちょっと暖かくなるからさ、もらってよ」
「いらんと言っとるだろうが!! このくそガキ!! あっち行け!!」
おっさんは樅山の手を振り払って、ギターを手にした。
「あ、」
あのおっさんは、わかってるんだ。
樅山が……樅山が、やっていることが。
「おじさん、あのさ」
樅山が懲りずにおっさんの手をつかもうとした途端、
おっさんの目が、歌っているときのようにぎらりと歪んだ。
やばい。
「やめろって樅山!!」
オレはとっさに樅山の腕をつかんで、おっさんから引き離した。
「おっさん、ごめんな、いい夜を!!」
おっさんの顔をもう見たくなくて、オレは樅山を引っ張って逃走した。
おっさんがライブしてた暗い通りを抜けて、大きい道に出た。
クリスマスなんて関係ないねとでも言うような、いつもどおりの古本屋の前に、ベンチを見つけて座った。他のきらきら光っている店の前のベンチはアベック専用となっている。
中学、高校と帰宅部のオレは、走って上がった息をぜーはーさせながら、樅山の腕から手を離すと、ヤツは「あともう少しだったのに」と言ってオレを睨んできた。
「丹羽……何で邪魔したんだ」
息を乱さず笑顔で問いかけてくるこいつは心底怖い。「目が笑ってない」という表現はマンガとか小説に使うものだと思っていたが、まさかリアルに使う日が来るとは。
「お前こそ、何で、そんなに必死なんだよ」
オレの肩で息をしながらの問いに、樅山は返す言葉を探しているのか、何なのか、何も言わずにじっとしていた。
「おっさんのあの目、見てなかっただろ。
やばいってあれ。樅山、くんは」
「……樅山でいいって呼びづらいなら」
「樅山は、おっさんをもっと不幸にしてどーするんだよ」
返事は、なかった。
走ったせいで温まった身体が、ベンチとの接触部分から急激に冷えていく。
寒い。早く家に帰りたい。
ケータイを開けば、母からの着信履歴が数件現れた。
留守電の内容は、何やってんの早く帰ってきなさいといったところだろう。
8時30分か。早く家に帰ってこたつでごろごろしたい。
耳に届くクリスマスメロディは、もはや他人事だ。
小さいころって、クリスマスの日にはすごいわくわくしてたはずなのに。
それはプレゼントがあるから、という理由ももちろんあったが、それだけじゃないんだ。
あの気持ちって、なんだったんだろう。
「オレ、修行中の身なんだ」
唐突に、それでいて静かに、樅山が始めた。
見れば、樅山はひざの上で両手を組み、そこに額を乗せていた。
むかつくけど、こういう格好がサマになるヤツなんだ、こいつは。
「丹羽ってさ、サンタ信じる?」
「どこかにいるんじゃないか、っていう夢くらいは、持ってる」
小さいころ見たどのアニメも、サンタさんは必ずどこかにいるんですよ、とかサンタの島があるんですとか、サンタの存在をほのめかして終わる。
枕元にプレゼントを置いてくれていたのが父さんや母さんだとわかった小5の冬はさすがにショックだったが、それでも、存在は……信じていたかった。
「よかった、丹羽がいいやつで」
樅山はたいしてよかったと思ってなさそうな声色で言ってのけた。
「オレのじいちゃんが、サンタの一人なんだ、実は」
「へぇ」
……。
!?
「は!? ってか……は!?」
「あ、信じちゃう?」
樅山はおもしろそうににやりとしたが、
そういうことじゃなくてだな、言ってて恥ずかしくないかとか意味わかんねえとかいろいろ言いたいけど、とりあえず、
「それで?」
続きを促すのが先だ。
樅山はニヤリ笑いをすっと引っ込めた。
「まあ、後継者問題なわけだ。
親父はサンタをそもそも信じないし、信じたとしても、そんな面倒なのの後は継がないって断固拒否。じいちゃんと親父、昔それに関して大ゲンカになったっぽいってのは母さんから聞いたんだけど。
オレも最初は、親父サイドだった。去年じいちゃんが倒れるまでは」
そこで樅山は息をついた。「よくある話だよ」と呟くヤツの顔には痛みがにじんでいた。
今までヤツがしてきた中で、一番ヤツらしい表情だった。
「すぐ退院したけど、サンタの仕事ってハードで、体力がないとやっていけないんだ。
だから、今年がじいちゃんの最後の仕事だった。昨日のイブの夜から、今朝にかけて、じいちゃんは担当地域をめぐった。オレも一緒に行った。
でも特に部屋に忍び込んでプレゼントを置いたりはしなかった。というより、想像してたような白い袋さえ持たずに、ただ夜の空をソリで散歩していた。
なにやってるんだろうって、わからなくなった。それで聞いたんだ。サンタの仕事って、何なんだって」
目の前の道路を、市バスが通り過ぎた。
オレは今、とんでもない話を聞かされているのかもしれない、という予感が体に走る。
永遠にナゾでよかった秘密を、とうとう聞かされてしまうのかもしれない。
そうしたら、オレのクリスマスはどうなってしまうのだろう。
この時点で大方の想像を壊されてはいる。プレゼント持って子どもの家回ってるんじゃないのかよ、と。それでも肝心な部分が未だ明かされずに残っている。
サンタに抱いたナゾの期待、クリスマスの日の不思議な感覚、そういうものの正体が今すべてわかってしまうんだとしたら。
オレ個人としての、クリスマスは、どういうものになるのだろう。
けれど、話をやめろ、と言う気はしなかった。
樅山がふっと表情をやわらげた。
「『幸せの期待をプレゼントするのがじいちゃんの仕事だ』」
ああ、結局。
ナゾは、ナゾのままだ。
「嫌いじゃない、と思った」
おう樅山、オレもそう思った。
幸せをプレゼントするんじゃない。
幸せの予感を、期待を、気持ちを、心を、プレゼントしている。
期待は、きれいじゃない。
裏切られることもある。
期待しかプレゼントできない。
それがサンタクロースの仕事。
樅山は背を伸ばして、隣に置いておいたかごを持ち上げた。
「だからオレ、今下積み中なんだよねー。24日に働くのはまだ早いんだと」
「で、言いつけられた仕事が、飴配りか」
「そう。ノルマ一人って言われた意味がわかるよな、これじゃ」
さっきから樅山の表情は、あの冷笑製造マシーンのようなものではなくなっている。
あ、この顔は。
オレは飴の入ったかごをひったくった。
「泣くなって」
「は!? な、泣いてねーよバカ!!」
そうか? なら何で思いっきり動揺してるんだ。
おお、涙ぐんでるじゃん樅山おもしろい。
なんだか楽しくなってきたので、オレは天を仰いだ。
「サンタさーん、あなたの孫がオレのことバカって言ってまーす!」
「ちょっ、ちょおおおぉぉ!!」
樅山があせって、オレの口を手で覆ってくる。
なんだよ、このカオ。
あせりすぎだよ。
「ぷっ、ははっ」
あー、おかしい。
オレが笑い始めたのを、樅山がきょとんと見てる。
多分、隣のベンチのカップルもオレを見てる。二人だけの世界を邪魔されたって顔してる。
おもしろい。愉快愉快。
「……は、ははははっ」
なんだ、樅山も笑うのか。
ていうか樅山、笑えるんじゃねぇか。
まあいい、クリスマスの夜くらい、笑っていようぜ。
散々笑って、寒さにちぢこまっていた身体もほぐれてきたところで、その腹の底をくすぐり回すような波もおさまりつつあった。
樅山からぶん取ったかごの中で、飴がガサッと音をたてる。
樅山があせる理由は、なんとなくわかった。
早く一人前にならなきゃって思ってたんだろう。
でもおっさんを不幸にしてちゃ、まだまだだな。
「樅山さ、不幸を報酬にするとか、もう言うなよ」
樅山は視線を落として、小さく「ああ」と言った。
その後、さらに小さくくぐもった声で、ぼそぼそ何か言うのが聞こえた。
「は? なんだって?」
あえて聞き返してやると、樅山は耳を赤くして、顔を上げた。
「それよりそれ、早く返せって!!」
もちろん、樅山の呟きは聞き取れていた。だけどさあ。
「サンキューな」なんて言われなくても、そのへんの気持ちはお前のその冷笑マシーンじゃない表情見てればわかるんだよ。
なんてことは言わないでおこう。
オレが言うとキモいから。
「言われなくても返すよ、サンタ見習い」
樅山はかごを受け取ると、顔をオレに背けてよっこらしょと腰を上げた。
顔を隠しても無駄なんだけどなぁ。赤くなってるの耳だから。ま、いっか。
「行くのか?」
「行くとも」
赤鼻のおっさんにも、幸せの期待を届けに。
メリークリスマス、どうか幸せなクリスマスを。
<あとがきとオマケの会話>